ホーム > 子育て・教育 > 子ども・若者支援 > 子どもの居場所・活動の場 > としま子ども食堂ネットワーク > 子ども食堂の開設をお考えの方へ
ページID:42480
更新日:2024年8月6日
ここから本文です。
子ども食堂の開設をお考えの方へ
子ども食堂とは
- 豊島区の場合は、NPO法人や団体、個人、飲食店が「子ども食堂」を立ち上げ、ボランティアの方々が中心となって運営しています。(行政が特定の団体等へ委託している事業ではございません)
- 形態は子どもや親子のみを対象とした食堂、それ以外の大人も対象にした食堂、宅食やお弁当の配付など様々です。
- 会場は社員食堂や会議室、高齢者施設や個人宅、飲食店、お寺や教会など、いつもは「子ども食堂」の看板が出ていない場所がほとんどです。(行政による会場の斡旋・紹介などはできません)
- 開設頻度は1か月に1~2回、週に1回など様々です。ご自身のできる範囲での開設を推奨します。
- ボランティアの方々が集まり、子どもたちが集まり、自然と「子ども食堂」という居場所になっていきます。行政(子ども若者課)が「子ども食堂」という形態を認可するものではございませんし、子ども若者課に「子ども食堂」開設の届け出・申請は不要です。(別途、保健所への届け出については下記の項目をご確認ください)
開設を考える前に
子どもの支援に携わるとは?
- 怪我や事故防止といった従来の安全管理だけでなく、緊急時への備え、さらに子どもたちのためのセーフガーディング(安心・安全に過ごせる環境づくり)も子ども食堂に関わる大人の大切な役割のひとつです。
- 豊島区には、子どもの権利に関する条例がありますので、開設を考える前に是非ご一読ください。
子どもの貧困とは?
- 経済的な貧困・文化的な貧困・関係性の貧困(孤立)・実存的貧困(孤独や希望喪失など)もすべて「子どもの貧困」です。
- 経済的に問題がなくても、他の課題を抱えている場合もあります。
対象者は?
- 誰を対象にするかは、それぞれの子ども食堂で決めています(区が指定するものではございません)。ただし、安全確保のため、乳幼児は保護者と一緒、小学生以上でもアレルギー対策や宗教的な配慮など保護者の方の同意が必要ですし、緊急時には連絡がつく状況が必須です。
- セーフガーディングの視点からも、子どもと大人が二人きりになるなど、本人達にその意識がなくても周りから疑念を持たれるような状況を作らないようスタッフの配置などもお考えください。
子ども食堂ネットワークとは?
- としま子ども食堂ネットワーク会議という、子ども食堂を運営している方々、開設を考えている方々が情報共有をしたり、学び合ったりする場がございます。日程などの詳細は、としま子ども食堂ネットワーク会議日程・実施報告をご覧ください。
- スタッフは何名必要か、食事はどのくらい用意すればよいのか、申し込み方法はどうすればよいのか、など開設にあたっての疑問点がたくさん出た場合、すでに運営している方々にお聞きなるのが効果的であると思います(参考:豊島区内の子ども食堂)。なお、子ども若者課では運営方法の詳細についてお問い合わせいただいても回答ができませんのでご了承ください。
地域でのつながりとは?
- 多くの「頼れる場所」「頼れる人」を知っていることは、子どもにとっても大人にとっても大事な資源であり、社会との接点になります。子ども食堂も居場所のひとつです。
- CSW(社会福祉協議会所属のコミュニティソーシャルワーカー)や民生児童委員、無料学習支援や日本語教室を行っているグループの方、子ども若者支援のNPO団体等とつながっておくことも大切です。
主な連携先
- CSW(社会福祉協議会所属のコミュニティソーシャルワーカー) https://toshima-shakyo.or.jp/contents/csw.html
- としま子ども学習支援ネットワーク(通称:とこネット)https://toshima-shakyo.or.jp/contents/kurashi.html
- お役立ち情報・相談窓口をさがす https://www.city.toshima.lg.jp/429/asistoshima/2201181032.html
事前準備について
保険の加入
- 事故発生時の対応のため保険に加入することをお勧めしています。
- 民間保険会社の傷害保険や賠償保険、東京都社会福祉協議会(http://www.tokyo-fk.com/volunteer/gyoji.html)の行事保険があります。
- 区からの保険の指定はございません。
保健所への届け出
- 子ども食堂の場合、保健所への届け出は任意になっていますが、池袋保健所生活衛生課食品衛生グループに届け出しておくことを推奨しています。「小規模給食施設、ボランティア給食における食事の提供(開始・変更・廃止)届」
- 池袋保健所生活衛生課食品衛生グループは、食中毒に関すること、アレルゲン表示についてなども相談できる専門窓口です。
- 東京都福祉保健局のサイトには、小規模給食・ボランティア給食を始める方に向けたリーフレットもあります。以下のページをご覧ください。https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/syoukibo.html
感染症・食中毒予防
- 食品衛生(ノロウイルス・腸管出血性大腸菌(O157など)対策など)についてhttps://www.city.toshima.lg.jp/217/kurashi/ese/shokuhin/index.html
- 子ども食堂向けの、新型コロナウイルス感染症対策自己点検シートもご活用ください。https://musubie.org/news/2889/
開催時の注意事項
食中毒の場合
- 平日は、池袋保健所生活衛生課食品衛生グループ ☎03-3987-4177へご連絡ください。
- 夜間、休日は東京都保健医療情報センター「ひまわり」☎03-5272-0303(24時間)などへご連絡ください。
事故や怪我の場合
- 重大事故でない場合でも、保護者の方にお伝えしておきましょう。
- 予期せず起こりやすい事故とその予防方法、もしもの時の対処法は子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック(PDF:7,435KB)をご覧ください。(消費者庁)
事後報告
- 食中毒が発生した場合や警察、救急車要請をした場合には、ご対応後(休日の場合は翌開庁日)に、子ども若者課地域支援グループ☎03-3981-2187(平日8時30分~17時15分)へご報告いただけると助かります。
個人情報の管理
- 利用申込のメールや電話のメモの保管場所に注意し、個人情報を目的外使用しないこと。
- 受付時など他の方に名簿が見える状態になっていないかなどについてもご配慮ください。
- セーフガーディングの視点から、スタッフが子どもたちとSNSでの交流などをしないことはもちろんのこと、子どもたちに向けても呼びかけが必要です。
子どもの様子が心配になった場合
豊島区子ども若者総合相談「アシスとしま」
虐待が疑われる場合「豊島区児童相談所」
ご家族のこと、暮らしのことなど心配になった時
豊島区民社会福祉協議会CSW(コミュニティソーシャルワーカー)までご連絡ください。
https://toshima-shakyo.or.jp/contents/csw.html
区以外の支援情報
農林水産省
子ども食堂やフードバンクに対しても、政府備蓄米を無償で交付できるようになりました。
農林水産省HP「学校給食用等政府備蓄米交付について」(新しいウィンドウで開きます)
全国の子ども食堂
NPO法人全国子ども食堂支援センターむすびえ(新しいウィンドウで開きます)
広くボランティアのことや運営のことを知りたい時
東京ボランティア・市民活動センター(TVAC)「ボラ市民ウェブ」(新しいウィンドウで開きます)
書籍紹介
『子ども食堂をつくろう!人がつながる地域の居場所づくり』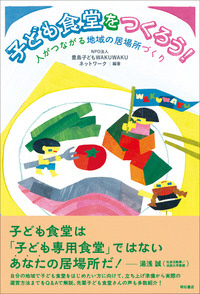
NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 編著
子ども食堂の立ち上げ準備から運営のコツまで、先輩子ども食堂の体験談を交えながら紹介しています。
(中央図書館、巣鴨図書館、目白図書館に所蔵されています)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2187