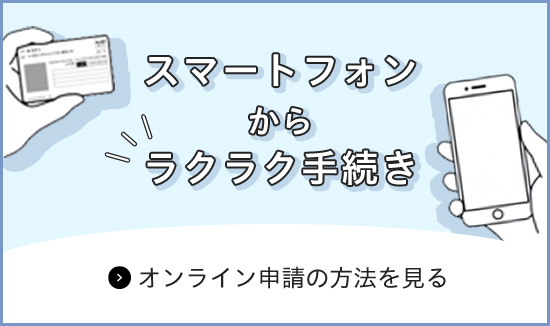ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援 > 手当・助成 > 子どもの手当・医療費助成 > 児童手当
ページID:2071
更新日:2025年10月31日
ここから本文です。
| ご利用いただける手続き方法 |
|
児童手当
児童手当とは、お子様を養育する父母などに支給される手当です。お子様が生まれたときや、豊島区にご転入されたときに申請してください。
なお、所得制限はありません。令和6年10月分の手当より撤廃されました。
【重要】児童手当現況届認定通知書(児童手当現況届認定兼支払通知書)の送付廃止について
令和6年度まで現況届の提出要・不要にかかわらず、年度更新時(現況時)の審査において児童手当の受給資格が認められたかたには、原則として9月下旬~10月上旬頃に「児童手当現況届認定通知書(児童手当現況届認定兼支払通知書)」を送付しておりましたが、令和7年度以降は上記通知書の送付を行わないこととなりました。資格の状況については、新規認定時の「児童手当 認定通知書」、「児童手当 額改定通知書」、「児童手当 支給事由消滅通知書」にてご確認ください。
※令和7年8月1日時点で令和7年度の児童手当現況届が認定されていないかたには、8月上旬頃に「児童手当 支払差止通知書」を送付します。こちらの通知が届いたかたについては、令和7年8月12日(火)に令和7年6月分~令和7年7月分の児童手当の振込はございません。
- 支給対象となる児童
- 手当を受けられるかた
- 手当の支給月額と支給方法
- 手当を受けるには
- 認定請求手続き
- 額改定請求手続き
- 現況届
- その他変更手続き
- 振込口座等の変更
- 公務員になったとき
- 海外に転出するとき
- 受給者が亡くなったとき
- 保護者の所得が変動したとき
- 受給者等の状況が変わったとき
- 児童手当受給者が子と別居することになったとき
- お知らせ
支給対象となる児童
高校生年代までの児童(18歳に達した後、最初の3月31日までの児童)
手当を受けられるかた
区内に住所があり、対象となる児童を養育している保護者(児童の両親のうち、いずれか当該児童の生計を維持する程度の高いかた)
- 生計を維持する程度の高い方については、住民税の情報をもとに判定しています。
- 保護者または児童が外国籍の場合、在留資格が短期滞在や興行のかた、または在留資格がないかたは受給できません。
- やむを得ない事情により、住民登録が出来ずに区内に居住している場合には、子育て支援課までお問い合わせください。
- 保護者が区内に居住していれば、対象児童は区外に居住していても支給対象になります。
- 支給対象の児童が日本国内に住所を有しないときは、原則として支給されません(児童が海外の学校に留学しているときは、受給できる場合があります。)。
- 父母が離婚協議中等で、別居している場合は、児童と同居している保護者に支給される場合があります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外に居住している場合)にも支給されます。
- 支給対象の児童が、児童福祉施設等に入所している場合、または、里親に委託されている場合は、原則として、その施設設置者等または里親に支給されます。
- 公務員のかたは勤務先から支給されます。手続きについては勤務先にお問い合わせください。
手当の支給月額と支給方法
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末などに転入・出生した場合については、前住所の転出予定日・出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、転出予定日・出生日の翌月分から支給されます。(土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日を含めて数えます。年末年始やゴールデンウィークも同様に含めて数えますので、特にご注意ください。)
- 転出予定日・出生日から起算した15日目が、土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、直後の開庁日を15日目とします。
- 支払い月の12日が、土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。なお、金融機関によっては、振込日が多少前後しますので、あらかじめご了承ください。
|
支給月額 |
支給方法(年6回) |
|---|---|
(第1子・第2子) :15,000円 (第3子以降) :30,000円
(第1子・第2子) :10,000円 (第3子以降) :30,000円
「第3子以降」の判定は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の兄・姉を含めて数えます。 |
10月(8月~9月分) 12月(10月~11月分) 2月(12月~1月分) 4月(2月~3月分) 6月(4月~5月分) 8月(6月~7月分)
|
第3子以降の加算について
支給対象となる高校生年代までの子に加え、大学生年代の子もおり、監護している子の合計人数が3人以上の場合は下記確認書の提出が必要です。電子申請・郵送・窓口のうち、いずれかの方法でご提出ください。
なお、令和6年10月1日時点で上記に該当する場合は、令和7年3月31日までに下記確認書の提出が間に合わなかったとしても、遡って差額分(加算による増額分)を支給できる可能性があります。遡ることができるかは、個別の事情によって異なりますので、子育て支援課までお問合せください。
電子申請
【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書(新しいウィンドウで開きます)
郵送・窓口
[申請書ダウンロード]【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:471KB)
[記入例ダウンロード]【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:611KB)
※窓口で手続きされるかたには、来庁時に上記確認書をお渡しいたします。
手当を受けるには
転入・出生等により豊島区であらたに手当を受けるかた、または既に手当を受給中で出生等により子どもが増えるかたは、手続きが必要です。
手続は、郵送、電子申請、窓口で行うことができます。
郵送の場合は、申請書等を児童給付グループまで郵送してください。ただし、郵送の場合は、申請書が児童給付グループに届いた日が申請日となりますのでご注意ください。(遅配・誤配などの郵便事故の責任は負いかねます。)
電子申請の場合は、ぴったりサービスを利用して電子申請してください。マイナンバーカードがなくても電子申請できます。ただし、乳幼児・子ども医療費助成の申請は電子申請でできませんので、別途窓口または郵送で申請してください。
窓口の場合、区役所本庁舎4階子育て支援課の窓口で申請してください。
※生計中心者の判定のため、受給者及び配偶者の住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要です。
子育て支援課の窓口受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時です。(祝日・年末年始を除く)
土曜日は総合窓口課で受付できる場合があります。お手続きの内容や世帯の状況等によっては受付できない場合もありますので、詳細は事前に子育て支援課までお問い合わせください。
認定請求手続き(豊島区で初めて児童手当の申請をする場合)
必要なもの
- 児童手当認定請求書
- 振込先の普通預金口座が確認できるもの(申請者名義に限ります。公金受取口座を利用する場合は不要です。)
- 申請者及び配偶者等の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 例:個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書等
- 申請者の本人確認書類
(1点で確認できる書類)
- 運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど、官公署発行の写真付きの身分証明書
(2点で確認できる書類)
- 健康保険証、年金手帳、住民票の写し、キャッシュカード、住民票記載事項証明書など
- 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の全員を記入してください。
- 申請者や児童の状況によっては、別途書類が必要になる場合があります。
- 各書類は、3か月以内に発行されたものを提出してください。
- 必要書類が不足していても、申請を受付します。ただし、実際に受給するためには後日すべての必要書類をご提出いただきます。
- 窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先「委任状について」をご参照ください。
- 児童手当の振込先として公金受取口座の利用を希望することができます。公金受取口座について詳しくは以下リンク「公金受取口座登録制度」をご参照ください。
[申請書ダウンロード]児童手当認定請求書兼乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書
電子申請(ぴったりサービス)児童手当認定請求の申請(新しいウィンドウで開きます)
公金受取口座登録制度(デジタル庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
額改定請求手続き(豊島区ですでに児童手当を受給している場合)
必要なもの
- 児童手当額改定認定請求書
- 申請者の健康保険証のコピー(3歳未満の児童を養育しているかたのみ)
※1 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の全員を記入してください。
※2 高等学校修了後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の児童について、受給者が新たに養育することになった場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
※3 受給者や児童の状況によっては、別途書類が必要になる場合があります。
※4 各書類は、3か月以内に発行されたものを提出してください。
※5 必要書類が不足していても、申請を受付します。ただし、実際に受給するためには後日すべての必要書類をご提出いただきます。
※6 窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先「委任状について」をご参照ください。
[申請書ダウンロード]児童手当認定請求書兼乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書
電子申請(ぴったりサービス)児童手当額改定請求の申請(新しいウィンドウで開きます)
現況届
毎年6月にご提出をいただいていた現況届について、公簿(住民票、税情報)等で受給者の所得情報等の支給要件について確認ができる場合には、提出を省略できることとなりました。ただし、毎年6月1日の状況を公簿等により確認することができない受給者については、引き続き現況届等の提出が必要です。提出が必要なかたには、5月下旬~6月上旬ごろに現況届を郵送しますので、ご提出ください。
提出が必要なかた
- 大学生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の第三子加算算定額算定対象の子の職業等が学生に該当しないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 住民票で住所が把握できない、法人である未成年後見人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる区市町村で受給しているかた
- 支給要件児童の戸籍および住民票がないかた
- 豊島区から現況届提出のご案内があったかた
なお、過年度分の現況届が未提出または不備の場合は、提出・不備の解消が必要です。
その他変更手続き
振込口座等の変更
児童手当の振込口座等の変更は電子申請もしくは郵送での手続きができます。ただし、変更は各支払月(12月・2月・4月・6月・8月・10月)の前月15日までに行ってください。変更手続きの時期によっては、お振込先が変更前の口座となる場合があります。受給者(現在の口座名義のかた)以外の名義には変更できませんのでご注意ください。
<電子申請>申請フォーム(児童手当・児童育成手当・児童扶養手当共通)(新しいウィンドウで開きます)
<郵送>口座振替変更届(PDF:99KB)に受給者名義の振込口座等を記入うえ、提出してください。ただし、申請書が児童給付グループに届いた日が申請日となりますのでご注意ください。(遅配・誤配などの郵便事故の責任は負いかねます。)
公金受取口座を振込先として指定されている(指定する予定)の方へ
下記にあてはまる場合は、上記口座振替変更届<電子申請/郵送>の提出が必要です。
- 児童手当の振込先に新たに公金受取口座を指定する場合
- 公金受取口座の登録を抹消した場合
下記変更をした場合は、上記口座振替変更届<電子申請/郵送>の提出もしくは電話での連絡が必要です。
- 公金受取口座を児童手当の振込先としている方で、マイナポータルで公金受取口座情報を変更した場合
連絡先(電話):03-3981-1417 豊島区役所子育て支援課児童給付グループ直通 平日8時30分~17時00分(祝日・年末年始を除く)
公務員になったとき
公務員になった等の理由で、勤務先から児童手当が支給されることになった場合は、すみやかに消滅届を提出してください。電子申請でも手続きができます。電子申請する場合、申請者本人の電子署名が必須です。
電子申請(ぴったりサービス)児童手当受給事由消滅届(新しいウィンドウで開きます)
海外に転出するとき
児童手当の受給者が海外に転出する場合は、消滅届を提出してください。電子申請でも手続きができます。電子申請する場合、申請者本人の電子署名が必須です。
電子申請(ぴったりサービス)児童手当受給事由消滅届(新しいウィンドウで開きます)
また、児童が引き続き国内に居住する場合は、国内で児童を養育している人(配偶者など)が新たに児童手当を申請する必要があります。配偶者の児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、受給者が月末などに転出した場合は、転出した日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、転出した日の翌月分から支給されます。(土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日を含めて数えます。年末年始やゴールデンウィークも同様に含めて数えますので、特にご注意ください。)
認定請求書の提出については、「認定請求手続き(豊島区で初めて児童手当の申請をする場合)」をご確認ください。
受給者が亡くなったとき
児童手当の受給者だったかたが亡くなった場合、配偶者が新たに児童手当を申請する必要があります。配偶者の児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末などに亡くなった場合は、亡くなった日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、亡くなった日の翌月分から支給されます。(土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日を含めて数えます。年末年始やゴールデンウィークも同様に含めて数ます。)
認定請求書の提出については、「認定請求手続き(豊島区で初めて児童手当の申請をする場合)」をご確認ください。
また、亡くなったかたにまだ支払われていない児童手当が残っている場合、請求手続きが必要となります。支給対象児童の口座にお振込みいたしますので、未支払児童手当請求書をご提出ください。電子申請でも手続きができます。
電子申請(ぴったりサービス)未支払児童手当請求書(新しいウィンドウで開きます)
保護者の所得が変動したとき
保護者の所得が変動し、児童の生計を維持する程度が高い保護者が変わった場合、児童手当受給者を変更することが可能です。所得変動に基づく受給者変更を希望する際は、毎年5月1日~9月10日の間に、前受給者の受給資格消滅および新受給者の申請手続きをしてください。
手続きの詳細については子育て支援課までお問い合わせください。
※ 所得が変動した年度の児童手当が支給決定されてしまうと、所得変動に基づく受給者変更の受付はできませんので、あらかじめご了承ください。
受給者等の状況が変わったとき
以下に該当する場合は変更届をご提出いただく必要があります。
3歳未満の児童を養育している受給者で加入している年金の種別が変わった場合
【例:厚生年金(私立学校共済年金・公務員等共済年金等を含む)⇔国民年金等】
<電子申請>児童手当 氏名変更/住所変更等の届出(新しいウィンドウで開きます)
<郵送>[申請書ダウンロード]児童手当変更届(PDF:72KB)
※【国民年金または未加入→厚生年金(私立学校共済年金・公務員等共済年金等を含む)】に変更となった場合のみ、受給者の健康保険証コピーが必要です。上記変更届に添付したうえで、ご提出ください。
豊島区に住民登録をしていない状況で豊島区から児童手当を受給しているかたについて、受給者本人の氏名・住所を変更した場合や児童の氏名を変更した場合
<電子申請>児童手当 氏名変更/住所変更等の届出(新しいウィンドウで開きます)
<郵送>[申請書ダウンロード]児童手当変更届(PDF:72KB)
受給者が婚姻、離婚した場合
<郵送>[申請書ダウンロード]児童手当変更届(PDF:72KB)
※提出書類の内容によっては、追加でお問い合わせ等をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
その他変更手続きについては、お手数ですが子育て支援課児童給付グループまでお問合せください。
児童手当受給者が子と別居することになったとき
児童手当の受給者と対象児童が別居している場合、監護事実の同意書(児童と別居していても受給者が児童を養育していることを証明する書類)の提出が必要です。
記入例を参考にご記入ください。
※1 児童と同居している世帯の世帯主の自筆が必要です。
※2 児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
※3 児童が海外に留学している場合には別の手続きが必要となりますので、お問い合わせください。
[申請書ダウンロード]監護事実の同意書(PDF:140KB)
[記入例ダウンロード]監護事実の同意書(PDF:282KB)
お知らせ
令和6年度児童手当制度改正についてのお知らせ
制度改正にともなう児童手当の申請期限は令和7年3月31日(必着)となっておりました。申請期限までに制度改正に係る申請をされ、かつ、支給要件をみたすかたには、令和6年10月分に遡及して手当を支給しております。原則として令和7年4月1日以降の申請については、申請書が到着した日の翌月分から支給開始となりますので、あらかじめご了承ください。
※制度の詳細や申請方法等については、令和6年度児童手当制度改正についてをご確認ください。
児童手当支払証明書
住宅ローンや奨学金の申請等のために児童手当の支払証明が必要な場合、申請をしていただくことで「児童手当支払証明書」を交付します。
申請方法等については、児童手当支払証明書の交付についてをご確認ください。
児童手当旧制度について(令和6年9月支給分までの制度)
令和6年9月支給分までの児童手当の制度について、旧制度に関するページをご覧ください。
児童手当の手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になりました
平成28年1月から児童手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。
個人番号(マイナンバー)を記載した書類を提出する際に提示が必要な書類については、下記リンク先をご参照ください。
子どもの手当・医療費助成申請書類の個人番号(マイナンバー)の記入について
個人番号(マイナンバー)の記載が必要な申請書類
- 「児童手当認定請求書」申請者及び申請者の配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
- 「監護事実の同意書」申請者と別居している子どもの個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
- 「個人番号変更等申出書」登録している個人番号((マイナンバー)児童手当受給者、受給者の配偶者、受給者と別居している児童))が変更になった場合、児童手当受給者とその配偶者が離婚した場合、児童手当受給者が婚姻した場合には届出が必要です。
- 「【第三子加算用】監護相当・生計費の負担についての確認書」大学生年代の子どもの個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
なお、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)による情報連携が本格運用されたことに伴い、従来必要だった下記の添付書類が一部省略可能になりました。
- 申請者等の住民税課税(非課税)証明書
- 児童の住民票又は住民票記載事項証明書(当該児童が世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)
- 健康保険証の写し※ただし、公務員共済の組合員のかた(3歳未満の児童を養育しているかたのみ)は、引き続き添付が必要となります。
※ 状況により、従来通り上記書類の提出をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417