としまの魅力 > 知る > 資料館・美術館・博物館 > 豊島区立郷土資料館 > 郷土資料館 > 刊行物 > これまでに開催した特別展・企画展図録 > 図録(1990年度)
ページID:48890
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
図録(1990年度)
池袋の生活資料展─池袋ちょっと昔のくらし─
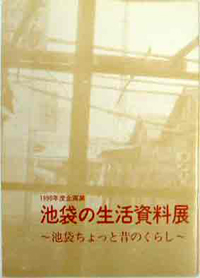
展示期間:1991年3月1日から3月30日
価格:300円
今回の企画展「池袋の生活資料展」は、昨年11月に実施した、池袋地区(池袋本町1から4丁目、上池袋2から4丁目、東池袋1丁目、池袋1から4丁目、西池袋1・3から5丁目)の「歴史生活資料所在調査」の際に寄贈を受けた資料を中心に展示しています。
池袋地区の歴史生活資料所在調査は、当初の予想をうわまわる成果を得ることができました。
その成果の一つは、生活資料そのものの残存状況です。
今回の調査区域は、その大半を1945年(昭和20年)の空襲で焼失し、また、戦後の急激な都市化によって、その生活環境が著しく変えられていった地域です。また、戦後になってから、大変多くの人々が移り住んだ地域でもあります。
したがって、当初の予想では、調査対象の中心をなす戦前・戦中の資料はもちろん、1950年代後半までの生活資料さえも、はたして残存しているかどうかも心配の種でした。
しかし、いざ調査に入ってみると、この心配は杞憂におわり、多くの歴史生活資料の存在を確認することができました。
なかでも、意外なことに、戦前から使用していたというものが予想以上にありました。所蔵者の方の話を聞いてみると、以前住んでいた場所で焼け残ったものを、池袋に来てからも使用していたとか、戦時中に疎開していた時にも持っていったとか、その残り方もさまざまなようです。
このようにしてのこされたものを目にした時、年代や暮らし向きを特定する形では無理にしても、高度経済成長を遂げる以前のくらしを知る手掛かりになる展示は可能なのではないか、ということになりました。
今回の展示の企画はこのような考え方から出発しています。
(かたりべ21号より)
ミルク色の残像─東京の牧場展─(完売)
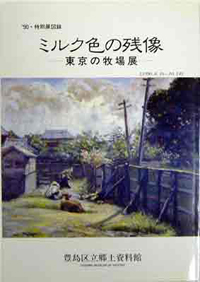
展示期間:1990年8月16日から10月14日
価格:900円
郷土資料館では、日本の酪農発展に重要な役割を果たしてきた東京の牧場に着目し、都内最初の試みとして東京の牧場展を開催いたします。
今回の特別展は、昨年度当館が行った旧西巣鴨町地区の歴史生活資料所在調査の成果をもとにしていますが、1987年度特別展「失われた耕地─豊島の農業─」での牧場コーナーが子どもたちに大きな反響を呼んだことが、東京の牧場を取り上げる直接の動機となっています。
ところで、明治中期から第二次大戦直後まで豊島区にはいくつも牧場があったかご存じでしょうか。高層ビルが立ち並び、人口密度が日本一高い今日の豊島区からは想像もつきませんが、区内のあちこちで乳牛の姿を見ることができました。
豊島区における牧場の創始者といえば、千葉から来た前田喜代松の名を忘れることはできません。1888(明治21)年、前田が鬼子母神前に「北辰社」(ほくしんしゃ)牧場を開いたのが豊島の牧場の始まりとされています。そしてこれ以降、区内には、角倉賀道(すみのくらまさみち)の「愛光舎」や田村貞馬(さだま)の「強国舎」など日本の牛乳搾取業を代表する牧場が、巣鴨・池袋地域を中心に次々と開設されました。そして1947年(昭和22年)に「桜木舎」が経営に終止符を打つまで、のべ60ヶ所の牧場が東京市民に牛乳を供給し続けたのです。
今回の特別展では、豊島区をはじめ都内に数多く存在した牧場の歴史を掘り起こし、その存在の意味を考えていきたいと思います。
(かたりべ19号より)
お問い合わせ
電話番号:03-3980-2351